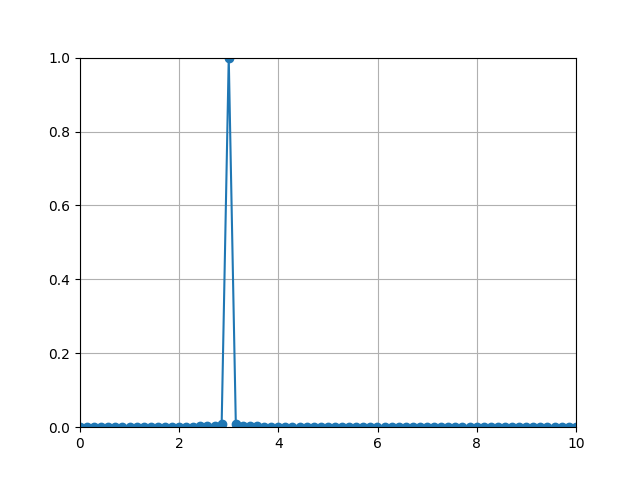「EXAFS振動をフーリエ変換する」というフレーズはX線吸収分光をやっていると腐る程見かけるが、実際にはArtemisやらLarchやらのソフトで流し込んで、実際に気にするところはパラメータのフィッティングだけということがほとんどな気がする。
ここでは「そもそもフーリエ変換するとはどういうことか?」について触れて行きたいと思う。
EXAFSについては、田渕先生の以下のスライドが非常に分かりやすい。
http://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1/lib/exe/fetch.php?media=nssr-long-201406.pdf
EXAFS振動 を超簡略化して、一つのsin関数(かつ余計な項(位相シフト)を含まない)で与えられるとする。これは最も理想的なEXAFS振動である。
を超簡略化して、一つのsin関数(かつ余計な項(位相シフト)を含まない)で与えられるとする。これは最も理想的なEXAFS振動である。
「理想的な」という意味は、フーリエ変換(波数 距離
距離 )すると、原子間距離(求めたい量)
)すると、原子間距離(求めたい量) のところで(原理的に)厳密に鋭いピークを持つ。(位相シフトなどゴチャゴチャ入ると、
のところで(原理的に)厳密に鋭いピークを持つ。(位相シフトなどゴチャゴチャ入ると、 からピーク位置が少しズレる)
からピーク位置が少しズレる)

("2"が付いているのは距離 を電子が「行って返って来る」ことに依る)
を電子が「行って返って来る」ことに依る)
これをいきなりフーリエ変換する前に、通常のやり方(信号解析(時間 周波数
周波数 ))を復習して、比較出来るようにする。
))を復習して、比較出来るようにする。
周波数 の信号
の信号 がsin関数で次のように与えられているとする。
がsin関数で次のように与えられているとする。

これをpythonを使ってフーリエ変換してみる。
import numpy as np
from scipy.fftpack import fft, fftfreq, fftshift
from matplotlib import pyplot as plt
N = 600
delta_t = 1.0 / 600.0
min_t = 0.0
max_t = N * delta_t
t = np.linspace( min_t, max_t, N )
f0 = 10
s = np.sin( 2. * np.pi * f0 * t )
plt.plot( t, s, "-o" )
plt.savefig( "s.png" )
plt.close()
tilde_s = fft( s )
tilde_s = fftshift( tilde_s )
tilde_t = fftfreq( N, delta_t )
tilde_t = fftshift( tilde_t )
plt.plot( tilde_t, 1.0/N * np.abs( tilde_s ), "-o" )
plt.grid()
plt.savefig( tilde_s.png )
plt.close()
plt.plot( tilde_t, 2.0 * 1.0/N * np.abs( tilde_s ), "-o" )
plt.xlim( 0, 50 )
plt.grid()
plt.savefig( tilde_s.png )
plt.close()



 に対応したピークがキチンと得られている。
に対応したピークがキチンと得られている。 - sin関数のフーリエ変換なので、負の振動数成分と対で現れる( cos関数も同様)。
- 規格化は
 。
。 はメッシュ数(今の場合、
はメッシュ数(今の場合、 )。
)。
- そのため、正の振動成分のみをプロットする場合、二倍しないと一見規格化が保たれていないように見える。
- フーリエ変換後の
 の範囲は
の範囲は ](今の場合、
](今の場合、 、[
、[ ])。
])。
- これに対し、
 (今の場合、
(今の場合、 )。
)。
- したがって、幾ら細かく(
 )データを取っても、元データのデータ範囲
)データを取っても、元データのデータ範囲 が変わらないとフーリエ変換後のメッシュは細かくならない。
が変わらないとフーリエ変換後のメッシュは細かくならない。
単純にフーリエ変換すると、固有振動数 の位置にピークが得られたわけだが、これはつまり横軸が振動数(
の位置にピークが得られたわけだが、これはつまり横軸が振動数( )に変換されており、角振動数
)に変換されており、角振動数 ではない。
ではない。
 に変換するには、以下の2パターンが考えられる。
に変換するには、以下の2パターンが考えられる。
1.  の位置にピークが出て来ると解釈する。
の位置にピークが出て来ると解釈する。

より と思える。
と思える。
2. 横軸 に
に を掛けて、
を掛けて、 に変えてしまう。(
に変えてしまう。( )
)
さて、ここでEXAFSの話に戻る。 だったので、この形は
だったので、この形は に近い。
に近い。
やりたいことは、「 をフーリエ変換して、
をフーリエ変換して、 にピークが出る動径分布関数を得る」ことである。なので、
にピークが出る動径分布関数を得る」ことである。なので、
 ではなく、
ではなく、 でフーリエ変換する。
でフーリエ変換する。 は
は ではなく
ではなく に対応しているので、横軸
に対応しているので、横軸 に
に を掛ける。
を掛ける。
これを踏まえて、 から動径分布関数を得る。
から動径分布関数を得る。
import numpy as np
from scipy.fftpack import fft, fftfreq, fftshift
from matplotlib import pyplot as plt
min_k = 2
max_k = 12
delta_k = 0.1
k = np.arange( min_k, max_k, delta_k )
N = len( k )
R0 = 3
k2 = 2. * k
delta_k2 = 2. * delta_k
chi = np.sin( R0 * k2 )
plt.plot( k, chi, "-o")
plt.savefig( "chi.png" )
plt.close()
tilde_chi = fft( chi )
tilde_chi = fftshift( tilde_chi )
tilde_k2 = fftfreq( N, delta_k2 )
tilde_k2 = fftshift( tilde_k2 )
R = 2. * np.pi * tilde_k2
plt.plot( R, 2.0 / N * np.abs( tilde_chi ), "-o" )
plt.xlim( 0, 10 )
plt.ylim( 0, 1 )
plt.grid()
plt.savefig( "tilde_chi.png" )
plt.close()


 の付近にピークが得られているのがわかる。しかし、綺麗なピークとは言い難い。
の付近にピークが得られているのがわかる。しかし、綺麗なピークとは言い難い。
これは の範囲を広げると改善される。
の範囲を広げると改善される。
 ]にすれば、
]にすれば、

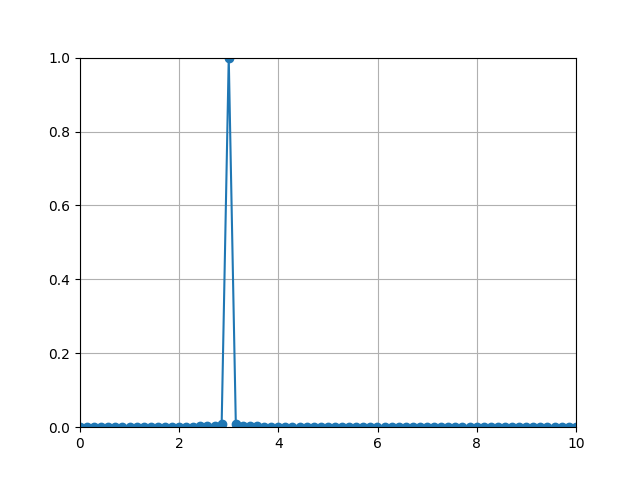
しかし、現実的には の実験データを得ることは難しい。
の実験データを得ることは難しい。
そこで、「窓関数が掛かっている」と見做して、ゼロ値のデータを足したものをフーリエ変換する。


ピーク強度が小さくなり、周りに小さなピーク構造が現れたが、その代わりにデータ点が増えて滑らかな関数を表すようになった。
これが、Artemis等のソフトで行われている有限フーリエ変換である。窓関数を掛けるのはデータの一部「のみ」でフーリエ変換するのではなく、追加でゼロデータを足しまくって無理矢理滑らかなピークにすることの宣言でもある。
これによって、一見、十分なデータ数があるように見えてしまい、「fittingパラメータを増やすためには広い の範囲と十分大きな
の範囲と十分大きな が必要」と言われても全然しっくり来なくなってしまっているのである。
が必要」と言われても全然しっくり来なくなってしまっているのである。
実態は、汚いピーク(少ないデータ点)を与えたフーリエ変換であり、それに対してfittingをすると思うと、「もっとたくさん(フーリエ変換後のピーク近傍の)データ点が欲しい!」と思えるのではないだろうか?
を、基底関数
で展開し、その展開係数を
とする。
は、消滅演算子
を用いて、次のように書ける。
は完備性により次の関係を満たす。
を真空状態
に作用させた波動関数を考えると、
は、本当に位置
にだけ粒子の存在確率を与えることがわかる。
の粒子を足す」とかだと波動性が発生していることになり、注意が必要だと思う。