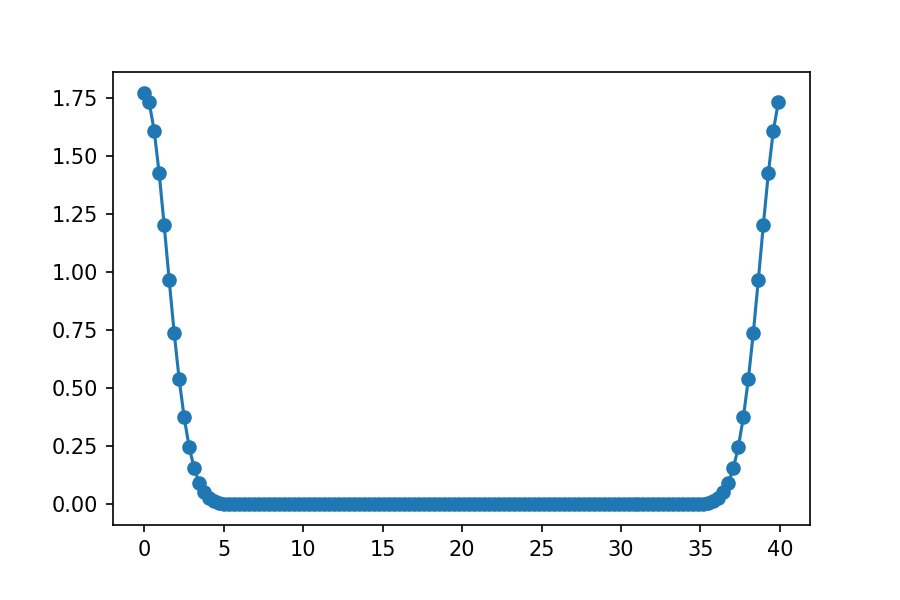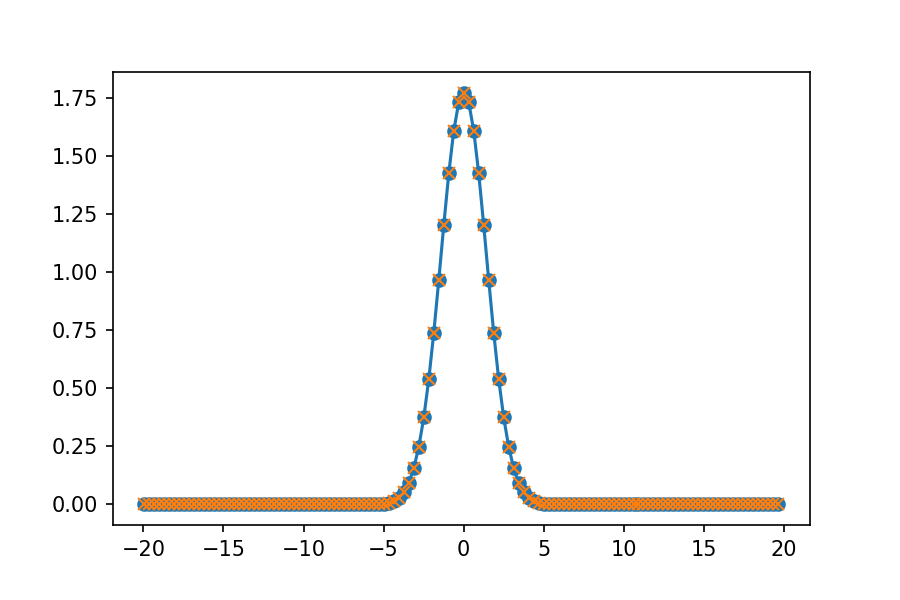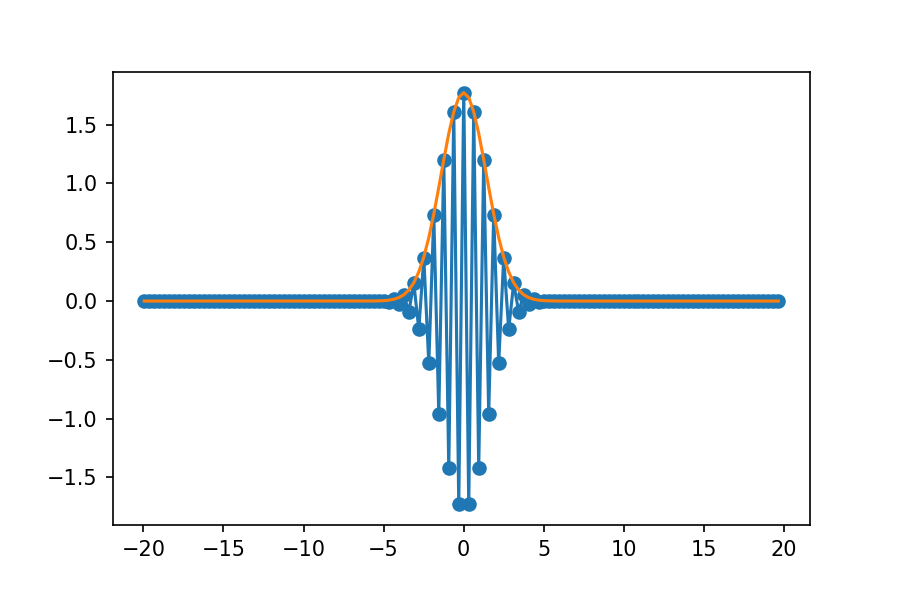ガウス関数はフーリエ変換しても、数式上は(幅は変わるが)またガウス関数になる。
高速フーリエ変換(FFT)とフーリエ変換との関係を以前まとめたため、FFTを用いてガウス関数をフーリエ変換する。
koideforest.hatenadiary.com
ここではscipy.fftpackを用いてFFTを行うが、(少なくともこの場合)出力される配列データの並びが「(正の振動数のデータ)、(負の振動数のデータ)」となっており、そのままプロットするとガウス関数に見えない。
試しにやってみる。
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fftpack import fft
a = 1
f = lambda x: np.exp( - a * x**2 )
max_x = 10.
min_x = -10.
N = 2**7
x = np.linspace( min_x, max_x, N )
data = f( x )
delta_x = x[1] - x[0]
tilde_f = fft( data ) * delta_x
delta_k = 1. / delta_x / ( N - 1 )
k = np.arange( 0, 1./delta_x + delta_k, delta_k ) * 2. * np.pi
plt.plot( k, abs( tilde_f ), "o" )
plt.show()
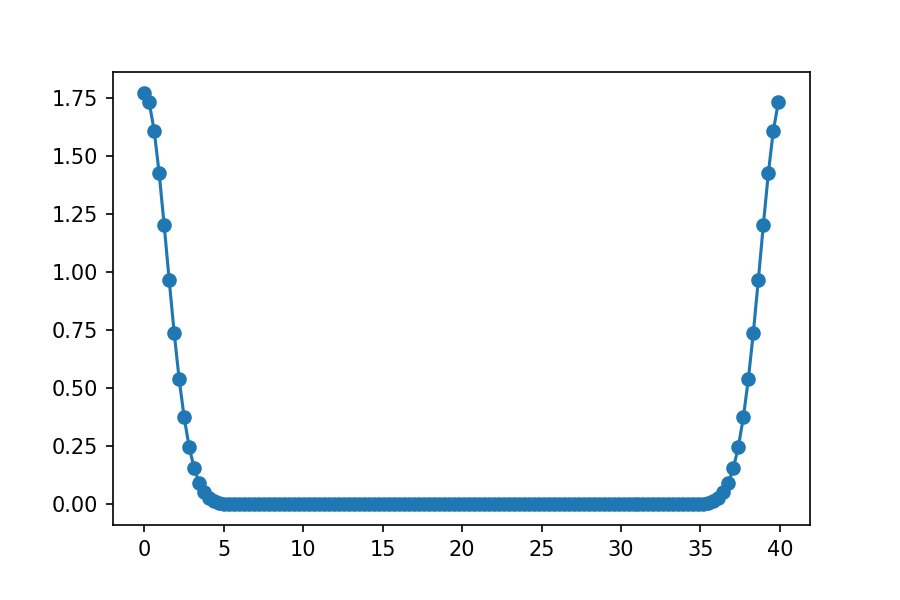
データの並びに関しては、以下のサイトが参考になる。
fft - memoring
SciPy FFTpack
Fourier Transforms (scipy.fftpack) — SciPy v1.1.0 Reference Guide
もう少し説明すると、FFTにおけるアルゴリズムの性質上、fft で生成した配列は、直感的な[ -N/2, ..., N/2 ]という順番では無く、
[ 0, 1, ,2, ... (N/2 - 1), N/2, -N/2, (-N/2 + 1), ..., -1 ]
という風になっている。
つまり、
[ (正の振動数:昇順)、(負の振動:降順)]
である。
fftpackに内蔵されている fftfreq を使うと、fft と同様な並びの横軸を作成してくれる。
from scipy.fftpack import fftfreq
freq = fftfreq( N, delta_x ) * 2. * np.pi
plt.plot( freq, abs( tilde_f ), "-o" )
plt.show()

点でプロットするならば問題無いが、線を追加すると N/2 → -N/2 に移るときの線が現れてしまう。
そこで、配列の並びを直感的に戻してくれる関数 fftshift が用意されている。
from scipy.fftpack import fftshift
tilde_f_shift = fftshift( tilde_f )
freq_shift = fftshift( freq )
gauss_k = lambda k: np.sqrt( np.pi / a ) * np.exp( - k**2 / ( 4. * a ) )
plt.plot( freq_shift, abs( tilde_f_shift ), "-o" )
put.plot( freq_shift, gauss_k( freq_shift ), "x" )
plt.show()
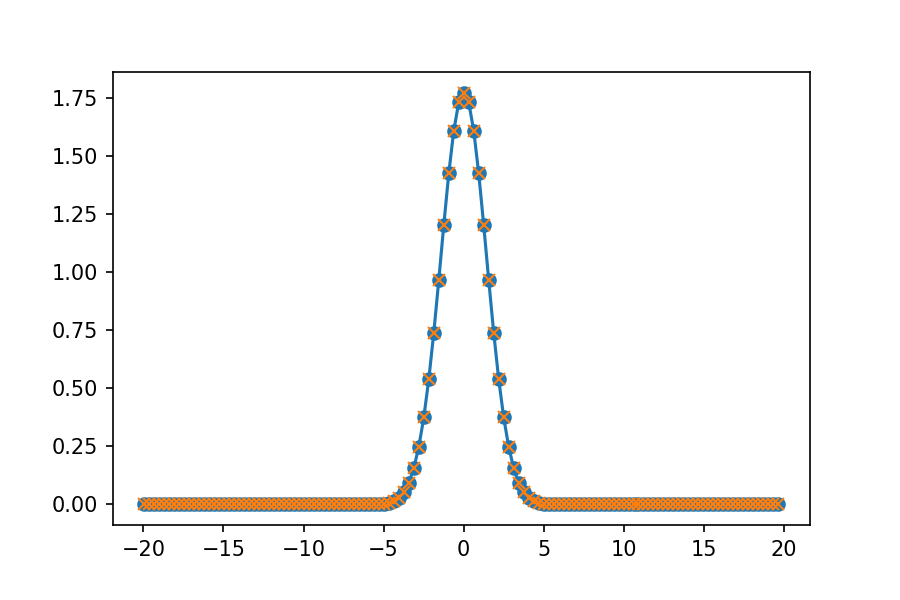
解析的に求めた解も一緒にプロットした。

解析解の導出は以下のサイトが分かり易い。ただし、指数の係数 は省略されている。
は省略されている。
ガウス関数のフーリエ変換 | ポップラーン
しかし、FFTを用いたガウス関数のフーリエ変換で最も問題なのは、実は数値解が振動している点である。
虚部は実部に比べて小さいため、実部のみプロットすると、
plt.plot( freq_shift, tilde_f_shift.real, "-o" )
plt.plot( freq_shift, abs( tilde_f_shift ), "-" )
plt.show()
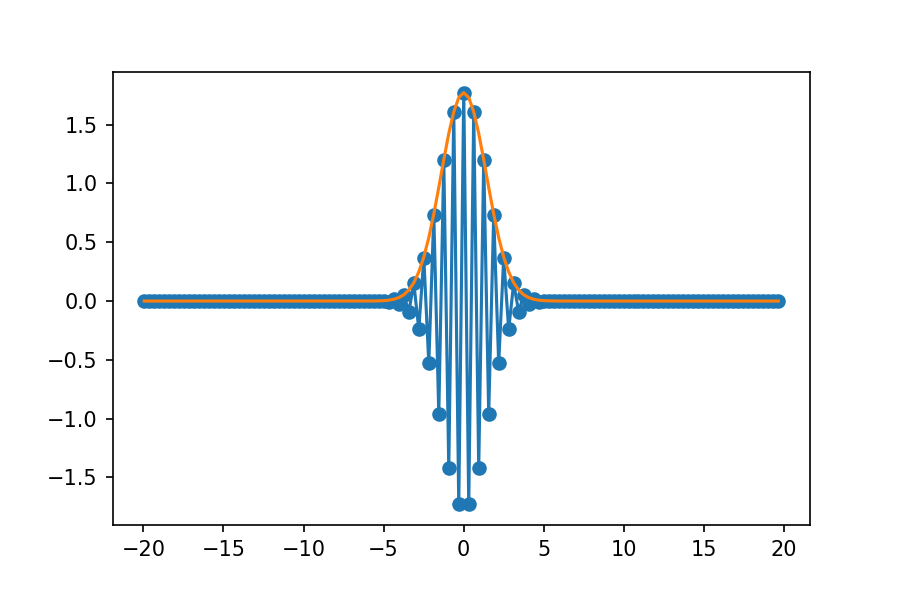
何故、振動が現れるのかは、今の所パッと思い付かないが、フーリエ変換はなかなか侮れないことを教えてくれていると思う。
の条件を除いた時に
と
の間で本当に相関があるのかをチェック出来る(らしい)。